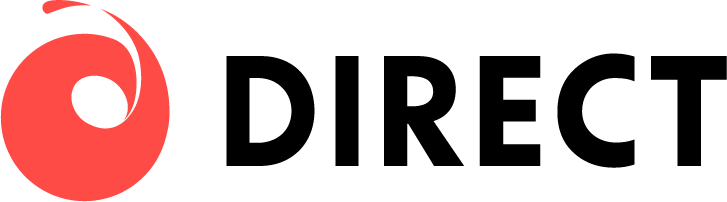Technology And Media
技術とメディア
圧倒的な開発スピードで
情報流通を加速する
なぜ開発スピードに
こだわるのか?
私たちの事業の本質は、良質な知識や情報を広く流通させることです。かつてこの役割は紙の書籍や雑誌、TVやラジオなどが担っていましたが、現在はデジタルメディアへと主戦場が移っています。
デジタルの世界では、何をするにもエンジニアの力が必要です。どんなに素晴らしいアイディアも、それを実現するシステムがなければ絵に描いた餅に過ぎません。
それに加えて、WEBビジネスの世界では、変化が激しく、数年で競争環境がガラッと変わってしまいます。新たなプラットフォームの登場、ユーザー行動の変化、技術トレンドの移り変わりなどが、私たちの、マーケティングや、コンテンツの提供、データ管理などに大きなインパクトを与えます。
そのため、ビジネスサイドと同じく、そのインフラとなる技術開発サイドでも、変化に素早く対応することが必要になると考えています。
DPGでは、紙媒体しか扱ってなかった創業の頃より、自社エンジニアによる内製開発にこだわってきました。これは、私たちが、過去約20年間に渡って、事業の変化、顧客の変化、技術や環境の変化に対応できてきた最大の要因です。
開発スピードを
上げる障害

出版業界やメディア業界では、テクノロジーの内製化が非常に稀です。多くの企業と同じく、システム開発をSIerに外注する構造が、開発スピードの大きな障壁となっています。なぜなら、外注では「速さ」よりも「期日と予算の確実さ」が優先されがちだからです。
そのため、新機能の実装やシステム変更に数ヶ月を要することがまだ一般的です。私たちは、時に、それを一週間程度で実装することができます。
日本と米国の大きな違いは、エンジニアの位置づけです。米国では自社内でエンジニアを雇い、事業と技術が一体となっている企業が多い一方、日本では外部に頼むモデルが長く続いてきました。
この仕組みには根本的な問題があります。外部に頼むと、事業と技術の間に距離が生まれ、スピードを上げる動機も働きにくくなります。また、変更するコストが高く、責任の所在も複雑になるため、小さく素早く進める開発サイクルを実現するのが難しくなるのです。
DPGのアプローチ
私たちは最初から、システムを自社で作ることと最新技術を積極的に取り入れることにこだわってきました。これは単に技術が好きだからではなく、変化の激しい情報流通の分野で、市場に対応する速さと柔軟性を確保するためです。
結果的に、DPGのエンジニアチームは、現状、一週間で全チーム合わせて約10の機能開発があります。年間で言えば約500回のリリースになり、この頻度は、Googleが提唱する「4 Keys」の指標でも「ハイレベル」と評価される水準です。
それを可能にしたのは以下の要素があげられます
- 「使ってみて初めて価値が分かる」という考えのもと、小さく素早くリリースを繰り返し、ユーザーの反応で、素早く改善すること。これにより仮説から実装、検証、フィードバック、改善のサイクルを素早くまわすことができています。
- また、開発からリリースまでを自動化する仕組み(CI/CD)を全面的に導入し、テストの手作業を徹底的に自動化したこと。この自動化により、エンジニアは創造的な作業に集中でき、開発サイクルを大幅に短縮することできています。
- 事業とエンジニアの距離が近く、背景や目的を共有することで、素早い意思決定ができること。通常、数週間かかる意思決定が、数時間でできることも珍しくありません。
- 一つの開発チームを5~6人程度の小規模チームにすること。少人数チームが密にコミュニケーションを取ることで、阿吽の呼吸が生まれ、スピーディな開発が可能になっています。
などがあげられます。
最後に、最も大きな要素として、企業文化として、「素早い実験と改善を繰り返す」ことが、行動規範として、浸透していることも大きく、現代では、速さこそが、競争力の源泉だと、経営陣から一般社員まで理解していることがあげられます。
テクノロジーが
支える未来
DPGは名前こそ出版社ですが、実態は、書籍出版から、サブスクリプション、ライブ配信、オンライン講座などを、総合的に手がける、メディア企業です。このようなビジネスモデルが実現できて、かつ、市場の変化に素早く対応できるのは、自社の開発スピードがあったからこそです。
過去にもテクノロジー投資を通じて、新たなビジネスモデルへ次々と変化してきました。Amazonも本を売るECサイトから世界をリードするテクノロジー企業へと進化したように、私たちもテクノロジーとマーケティングの両方に優れた企業へと変革を続けています。